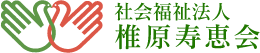理事長あいさつ/中川原三和子
医療法人 有馬病院は、昭和32年 加世田市に有馬外科医院として有馬哲三が開設致しました。その後63年を経て、現在は、内科・外科・消化器内科・脳神経内科・循環器内科・消化器外科・小児外科・婦人科・整形外科・リハビリテーション科・ペインクリニックの診療科を掲げております。一般病棟・地域包括ケア病棟(79床)を有する、強化型在宅療養支援病院として運営を行っています。時代と共に、病院に期待される役割は徐々に拡大して参りました。私共は日々の診療の中で、疾患の治療はもとより、患者様のかかえていらっしゃる諸問題に対する相談窓口となること、そして様々なニーズに応えるべく地域の中で保健・福祉分野における連携支援をはかること目指しております。地域社会を支えるインフラとして、当院はその責任をしっかりと果たして行く覚悟です。
今後とも皆様方のご支援ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。
令和6年 5月
医療法人椎原会 有馬病院
理事長 中川原 三和子
院長あいさつ/松本正隆
当院は昭和35年に旧加世田市の市街地、現在の南さつま市に有馬医院として開設され、今年で間もなく64年目を迎えます。平成6年に医療法人 椎原会 有馬病院 に改称、令和2年9月には現在の新築された医療施設となり、一般病棟、地域包括ケア病棟計79床を要する地域の中核病院として診療を行っております。当初から地域に根ざした外科、内科を中心とした診療は、時代とともにより細分化され、現在では消化器内科、脳神経内科、循環器内科、消化器外科、小児外科、整形外科、婦人科、麻酔科、ペインクリニック、リハビリテーション科の多くの専門性を備えた医療機関に発展しました。
開院当初からの当院の理念である地域住民への良質な医療の提供と疾病の予防、健全なる生活の維持を目指した医療は、高齢化社会の到来や独居世帯の増加とともに、老化により低下した心身機能の改善、日常生活維持や社会復帰のためのリハビリテーション、個人宅・施設への訪問診療に重要性が増しつつありますが、小児から働き盛りの成人も含めた身近な医療機関として、通常診療はもとより、外傷や救急疾患、感染症やがんなどの悪性疾患への対応、最新の知見・医療機器を駆使した適切な診断・治療、緩和ケア、他施設・医療機関との密接な連携、個人や職場を対象とした健診事業、人材不足が問題となっている看護師や介護士、リハビリ職を目指す学生の受け入れや教育、さらに海外からの人材の受け入れにも積極的に取り組んでいます。
今後も医療を取り巻く環境は決して明るいものばかりではありませんが、引き続き地域住民の要望、社会の要請に柔軟に対応しながら、職員一丸となってより良い医療の提供に努めて参りたいと思います。

令和6年5月
医療法人椎原会 有馬病院
病院長 松本 正隆