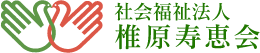「当院でこそ実現し得る、三位一体の健康増進医療」
副院長 武藤充
2025年2月14日(金)、15日(土)の2日間、パシフィコ横浜で第40回日本栄養治療学会が開催され、当院から2演題の発表をして参りました(口演セッション33「褥瘡・創傷治療」 高度るい痩、低栄養を伴うステージⅣ 褥瘡看護の経験-栄養支援の重要性を実感して-:筆頭演者 久徳美月 看護師.ポスターセッション49「高齢者」 高齢な慢性呼吸不全症例の脱フレイル成功体験~呼吸商に配慮した栄養支援とリハビリテーション療法介入のアウトカム~:筆頭演者 追田瞳 管理栄養士.)
本学会の源流は、小児外科医が世界に誇る手術、Kasai procedure の葛西森夫先生により発起された完全静脈栄養研究会です。のちに日本静脈経腸学会となり(これが私が初めて発表した全国学会で、思い出のある学会です。私の栄養学の師匠であります、髙松英夫先生から熱い戟を頂きながら、毎晩何時間もかけて学会準備をしたことを今でも鮮明に覚えています。)その後、日本臨床栄養代謝学会を経て、日本栄養治療学会として2024年4月から新スタートを切っています。現在の学会会員数は、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の多職種に渡り
24.335名に上る有数のマンモス学会となりました。
丸2日間、朝から夕方まで15の会場で熱いディスカッションが行われました。全員懇親会では、BEGINの特別ライブのもと、オリオンビールを片手に新たな日本の栄養治療の船出を共有してきました。
今回の大きな学びであったのは、栄養治療と看護の関わりでした。患者さんの置かれている社会背景の正確なアセスメントを基に、だれとどのように暮らしていくのかを思い描きながら “生きるを ともに つくる” ことが看護の真髄であるとのメッセージでした。当院でもこのような取り組みを一歩ずつ積み重ね、地域のみなさまの笑顔と健康をサポートして参りたいと強く感じました。そのために医師がすべき事も多く考えさせられました。
全国の様々な施設の実情を垣間見、比較するなかで、当院の大きな特徴に気づきました。それは、類をみないリハビリテーション専門療法士の充実度であります。患者さんの健康を増進するためには、 “原疾患の的確な治療”+“適切な栄養治療による生きる力の賦活化”+“テイラーメイドなリハビリテーションによる日常生活能力の向上”の三位一体支援が欠かせません。この役割を地域の最前線で果たし得る医療機関は少ないと思われますが、ここ、有馬病院では実現可能な人材がしっかりと揃っています。わたくしたちは、共生 ・ 奉仕 ・ 拓生 の理念のもと、南薩地域に根差した 『三位一体の健康増進医療』 を推進して参ります。